
マーケティング戦略部の佐藤 正さん(左)、古谷 章さん
プロがホームページ制作会社をご紹介するサービス「Web幹事」。
本記事ではWeb幹事をご利用いただいたお客様に、利用の経緯や実際の流れをお伺いします。
今回は株式会社DEECH様。中堅・中小企業のマーケティングを支援するスペシャリスト集団です。
Web幹事では2020年6月に、ポスティング業務の効率化とエリアマーケティングが同時にできるマーケティングサービス『DEECH(ディーチ)』のサービスサイト開設における制作会社の選定をご支援させていただきました。
- 適切な制作会社を選ぶためのポイント
- 制作会社のパフォーマンスを上げるコツ
- ホームページ制作を検討している担当者へのアドバイス
以上のお話を、マーケティング戦略部・執行役員の佐藤 正さん、マーケティング戦略部・課長の古谷 章さんに伺いました。「ホームページ制作を検討されている方」は、ぜひご参考ください!
※取材日:2020年10月6日、Zoomにてインタビュー。
【無料】プロにホームページ制作会社を紹介してもらう
ブラックボックスな「ポスティング業務」を変える!

ー本題へ入る前にサービス誕生の背景についてお聞かせいただけますか?
佐藤さん:Web広告が旺盛な世の中でも、ポスティングに関しては他には変えがたい部分があり、新聞折り込みが減っている中でも、需要が維持されています。
電通が毎年レポートしている「日本の広告費」にもあるように、アナログ施策は毎年2兆円くらいの市場があり、デジタル需要に押されることなく一定のニーズがあります。
ただし、成熟した市場であるが故、非効率でブラックボックスな面もある市場と認識しています。
ポスティングの手配は結構面倒なのですが、まず地図を手配して、エリアを組んで、どう人を歩かせるかを考えて…。これを発注主様と4~5往復くらいはざらにあるんです。
「もっとデジタル化して業務効率を上げられるはず!」
そう思ったのが『DEECH』を開発する最初の動機です。とりあえずベータ版を作り、そこから改良を重ねて今年の10月に正式リリースをしました。2年がかりのプロジェクトです。
ただし、サービスを広げるにあたり、「集客」に強いサービスサイトをつくる必要がありました。そこで「サイトの集客」と「サービス理解」を同時に叶えてくれる制作会社を探すために『Web幹事』さんに相談しました。
Twitter経由でWeb幹事を利用
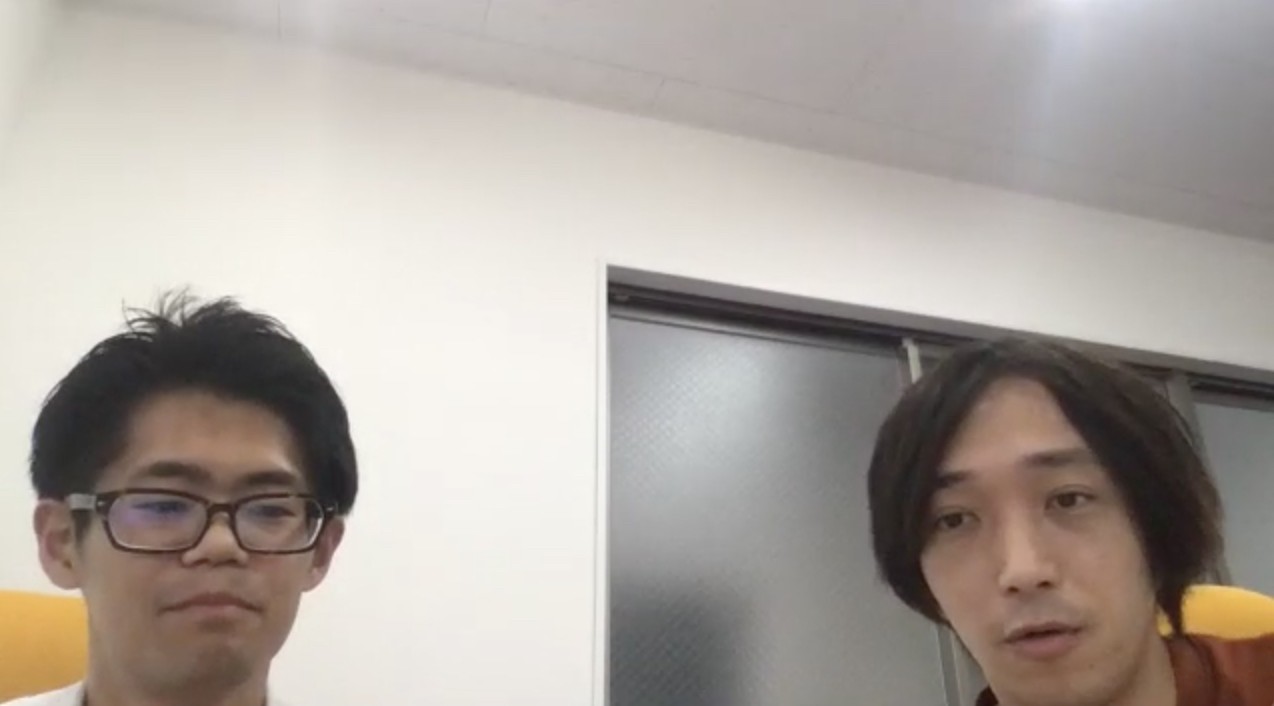
インタビューする筆者と峯村さん(右)
ー今回、Web幹事を利用されたきっかけが、Twitter経由だと聞いて面白いなと思いました。
佐藤さん:そこにいらっしゃる峯村さんをナンパしたのがきっかけです(笑)。
峯村さんのツイートを拝見するなかで、エンゲージメントをあげる術を持っていて凄いなと思い、しかも話しかけやすい雰囲気でした。いきなりDMを入れたので、峯村さんは「誰だ?」って印象だったと思いますが。

ー誰かの紹介ではなく、佐藤さんがTwitterを見てDMされたのが面白いですね。でも、社運をかけたプロジェクトを会ったこともない人に話すのに不安はなかったですか?
なかったですね。以前からTwitterを活用して仕事のつながりを増やしたいと思っていましたので。私自身、ビジネスに関してほとんど隠し事なく(笑)、Twitterでつぶやいています。

さとう@エリアマーケティング会社の編集者
実際、私のTwitterやnoteを見てくださって、商談の際に「見てます!」と言っていただける方が増えてきました。これからビジネスの可能性を広げていく新しい手段だと思います。Web幹事さんとつながったのも、Twitterがきっかけでしたから。
【無料】プロにホームページ制作会社を紹介してもらう
サイト制作後を考えてくれたWeb幹事

ー『DEECH』のサイトを作る上で、どんな制作会社を探していましたか?
佐藤さん:サービス誕生の部分でも申し上げましたが、『DEECH』の世界観、ビジネスを理解してもらえることはもちろん、サイトに「集客」できることが重要でした。
特に、コンテンツマーケティングで攻めようと考えていて、それを理解してくれる制作会社と仕事がしたいと思っていました。
デザインは制作会社のサイトを見れば実績が載っているので、自分たちの世界観に近い会社は探せます。しかし、サイトを制作した後の集客に関しては、公式サイトの情報では分かりません。
その点、発注側の「どうしたいか?」を直接聞いて寄り添ってくれるWeb幹事さんの人力のサービスは、ありがたいと思います。
ーでは、実際にWeb幹事に相談していかがでしたか?
ヒアリングしてくれた岩田さんは、こちらから何も伝えなくても「サイトが完成した後に何をしたいですか?」を詳しく聞いてくれました。その観点で制作会社を選んでくれまして、これが良い流れにつながったと思っています。
普通だったら、発注者がイメージしたサイトを作る会社を探そうとしますよね。納品することがゴールになりがちです。でも、岩田さんは、サイト制作後の先の目的を聞いてくれた。
先ほども言ったように、『DEECH』のサイトは制作後のコンテンツマーケティングが重要になります。それを詳しくお話ししたら、集客もコンテンツマーケもできる福島の制作会社を紹介してもらったんです。
ー「納品をゴールにしない」はWeb幹事が大切にしていることです。
言うは易しですが、中々できないことですよね。これが本当のヒアリングであり、適切な方向に導くディレクションだと思います。そこがWeb幹事さんの強さと差別化だと感じています。
しかも、岩田さんからは、サイト制作だけでなく、コンテンツマーケティングについてもレクチャーをもらいました。そのノウハウは確実に、『DEECH』のサイト内で活きています。
オンラインのやり取りに不安はなかった?

ーサイト制作のメイン担当である古谷さんにお聞きします。福島の制作会社ということで、オンラインでのやり取りに不安はなかったですか? Web幹事に相談される方の中でも、「対面じゃないと不安」とおっしゃる方がいます。
古谷さん:不安は一切なかったですね。制作会社さんもオンラインに慣れていて、納品までの流れも詳しく説明してくれました。チャットツールで質問したときもリアルタイムで返してくれて反応が早かったです。
定例会議はZoom、あとはSlack。オンライン会議とチャットツールのみでコミュニケーションをとり、1度も電話をしなかったです。制作会社さんがスプレッドシート(Googleが提供しているエクセルのようなツール)を見に行けば、現在の進捗もわかるようにしてくれました。
ー仕組みさえ整えれば、対面より効率化できる部分も多そうですね。オンラインだと、あまり意見交換が活発にできないイメージですが、その点はいかがですか?
いえ、意見もたくさんくれました。制作会社によっては、納品することが目的になりがちなので、こちらが提案した意見に対し「それでいいんじゃないですか」と相槌を打つだけのケースも多々あります。しかし、発注者側はバランスの取れた第三者の意見が欲しいものです。
その点、Web幹事さんが紹介してくれた制作会社は、率直に意見をくれて、そのおかげで、サイトのコアとなるテーマも決断できたんです。
ーイメージ通りのサイトを制作する以上のプラスアルファが生まれたのはすごい。具体的に教えていただけますか?
当初、我々は『DEECH』のアピールポイントを"業務効率の改善”にしようと思っていました。これまでの導入経緯を振り返ると、非効率の部分を解消できたことをたくさん見てきたので、そこが強みだと思い込んでいました。
でも、制作会社さんが「業務効率をアピールするなら、御社じゃなくてもいいんじゃないですか?」とズバッと言ってくれたんです。
そのおかげで、私も佐藤も腹が決まり、ポスティング業務の効率化とエリアマーケティングが同時にできるサービスであることをメインの訴求にしました。
【無料】プロにホームページ制作会社を紹介してもらう
制作会社のパフォーマンスを上げるコツ

ー佐藤さんにお聞きします。制作会社とやり取りする上で意識されたことはありますか?
佐藤さん:サイト制作に入るときに「制作会社さんにとっても自慢のポートフォリオになるよう、全力で制作をお願いします!」と念押ししました。
良い作品を作るためには、作り手に気持ちよく仕事をしてもらうことが大切だと思っています。
要件定義(発注側の要望と、その要望を実現する方法をまとめたもの)は大事ですが、ガチガチに固めすぎると、クリエイターの遊べる範囲が狭まってしまってテンションも乗り切らないことが多い(笑)。
主役はお金を払う側になりがちですが、むしろ逆。作り手のモチベーションを上げることが何より大切だと考えています。これは僕自身が編集者だということもあるかもしれません。
ーお客様インタビューを何度かしていますが、その意見は初めて聞きました。どちらかと言えば、要件をどう通すかを考える方が多い印象です。
我々の場合、Web制作をやっていた時期もあるので、その経験は大きいと思います。社内のクリエティブの人たちのテンションが上がるのは、やりたいことをできていることや、提案が通ったときなんです。
ただし、丸投げは絶対にダメです。「好きに作ってください」と言っても、宝の地図もないのに砂場を掘っているようなもの。これでは途方に暮れてしまいます。
特に「プロなんだからできるでしょ!」は禁句(笑)。魔法使いじゃないんだから、それは横暴です。一緒に宝の地図を作る感覚、そのための行動が大切だと思います。
サイトの納品後に制作会社さんから「とても紳士的な対応でやりやすかった」と言ってもらえたのはこちらも嬉しかったですね。
発注者と受注者の関係性を超える
古谷さん:私は発注者と受注者の関係性を超えることが大切だと思っています。そのためには、作ることがゴールではなく、その先の本当の目的を共感・共有してもらうことです。
クリエイターも作ることが楽しいのではなく、作ったものが社会に貢献できることが本当の喜びだと思うんです。
なので、制作会社さんが着手する前に『DEECH』を開発するに至った背景、世に出す目的、今後どうなっていきたいのかを理解していただきました。足並みを揃えられたことが良かったです。
おかげさまで、サイトリリース後の反応も良好で、今後は多くのお客様にサービスを知っていただけるよう、コンテンツを育てていきます。
【無料】プロにホームページ制作会社を紹介してもらう
ホームページ制作を検討している方へ伝えたいこと
ー最後に、これからホームページ制作を考えている方にアドバイスがあればお願いします。
佐藤さん:意思決定者がプロジェクトにコミットすることが大切だと思います。『DEECH』のサイト制作では、僕と古谷で意思決定を行っていました。
社内政治によって、サイト制作に支障をきたすのを避けるためです。担当者が制作会社とやり取りして、あとから上長に判断を求めると、やり直しも多いですよね。
そうならないよう、ミーティングの場にも意思決定者が居るべきです。せっかくお互いが話し合って決めたことでも、「結局、上長のOKが出ませんでした」となれば双方の工数に影響が出て誰の得にもなりません。
意思決定者がフルコミットすることで、制作会社さんも熱量を保つことにつながるはずですから。
ー貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。
Web幹事 担当者からメッセージ
本件のヒアリングを担当させていただいた岩田です。
まずお話を伺って印象的だったのは佐藤さんの熱量です。「このサービスにかける!」という想いがひしひしと伝わってきましたし、市場も魅力的。
一方でこれまでにないサービスのため、集客のための「打ち出し方」「マーケ戦略」については僭越ながら色々ご提案をさせていただきました。その上でマーケティングを担える制作会社をご紹介。いいプロジェクトになり、ほっとしています(笑)
Web幹事では納品以降も見据えてホームページ制作会社をご紹介することもあります。お客様にとって本当に必要なものを繋ぐサービスとして展開していきます。
Web幹事のご紹介
- ホームページ制作会社を探したいが、相談できる人がいない
- 本業で忙しく、なかなか時間がない
- 制作会社をどうやって選べば良いか、分からない
というお悩みは、Web幹事に非常に多くいただきます。
そのような際は、Web幹事にご相談ください。
ホームページ制作経験のあるプロのコンサルタントが丁寧にご相談にのります。
そして、目的やご予算に応じて最適な制作会社をご紹介いたします!
Web制作の業界を経験したプロが対応するから、安心してご相談いただけます!
コンサルタントのご紹介
 代表取締役
代表取締役
岩田 真
2015年にWeb制作会社を設立し、
3年間で上場企業を含む50社以上制作に携わらせていただきました。
ホームページ制作のオンライン相談窓口「Web幹事」は、35,000件を超える豊富な相談実績と幅広い知識で、お客様のあらゆるニーズにお応えします。
現在では毎月、数百件のWeb制作に関する相談に乗っています。
様々なお客様のWeb制作を実際に行ってきましたので、初心者の方でも安心してご相談ください!
相談から制作会社のご紹介まで、全て無料でご利用いただけます。
もちろん、紹介された制作会社に必ず発注する必要もありません。
ホームページ制作でお困り事がありましたら、お気軽にご相談ください!
【無料】プロにホームページ制作会社を紹介してもらう
